ゲーム産業の系譜
プレイステーションの父が語る半世紀
-
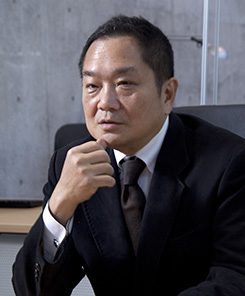
-
サイバーアイ・エンタテインメント株式会社 代表取締役社長兼CEO
久夛良木 健 - Ken Kutaragi
1950年、東京生まれ。1975年ソニー株式会社入社。第一開発部、情報処理研究所を経て1993年、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント設立。「プレイステーション」「プレイステーション2」「プレイステーション・ポータブル」「プレイステーション3」などの一連のプレイステーションフォーマットを生み出し、「プレイステーションの父」と称される。1999年、同社代表取締役社長、2006年、同社会長兼グループCEO、2007年、同社名誉会長を歴任。同時に、2000年にソニー株式会社取締役に就任。2003年にソニー株式会社副社長兼COOを兼任し、2007年の現役引退以降はシニアテクノロジーアドバイザーとして後進の育成に努めると同時に、2009年、自身の会社であるサイバーアイ・エンタテインメント株式会社を設立、代表取締役社長兼CEOに就任。現在、楽天株式会社、株式会社マーベラス、株式会社ノジマの社外取締役、立命館大学経営大学院客員教授、電気通信大学特別客員教授に就任。2008年にAcademy of Interactive Arts & Sciences(AIAS) から特別功労賞、Consumer Electronics Association (CEA) からCE Hall of Fame を受賞。
第1回『2001年宇宙の旅』で夢見たコンピューターの未来
2026年02月10日掲載
私が1975年にソニー株式会社に入社後の1983年から1988年までの間は、神奈川県の厚木にあった情報処理研究所に勤務していました。当時のソニーは、まだテレビやビデオ、ウォークマンなどのアナログ機器が中心でしたが、コンピューターや最先端のデジタル信号処理の研究がやりたいということで、当時の技術TOPだった森園副社長に頼みこんで傘下の研究所に引っ張って貰ったのです。
1983年頃というと、任天堂やセガから最初の家庭用ゲーム機がリリースされた時期です。MSXの登場もちょうどこの頃でしたね。ソニーというとコンシューマー向けAV機器を作っているイメージが強いかと思いますが、厚木工場では世界中の放送局向けに1台1千万円もするような放送用のカメラやVTR、映像編集システムなども開発・販売していたのです。
そこには当時、100名を超える新進気鋭のエンジニアや研究者たちがひしめいていました。最新技術に関わる研究開発テーマだけではなく、アメリカの技術系の大学に留学して戻って来た研究員も多かったことから、その頃運用が始まったばかりの商用インターネット回線を利用して、留学先の大学の教授や研究室のメンバーと常時やりとりをしていました。ですから、シリコンバレーにいるのと変わらないような状況でした。
皆さん好奇心が旺盛で、新しいアイディアを考え付いたり妄想したりすると、すぐに自分で取り組んでしまうような人たちばかりです。それぞれにテーマを持って研究開発に取り組んでいましたが、人によっては複数のテーマを抱えていて、毎日何が起こるのか会社に行くのが楽しかったですね。
私自身は、デジタル技術を活用した高密度磁気記録システムの開発に取り組んでいました。この磁気記録システムは、当時Appleの最初のMacintosh向けにも採用された3.5インチのフロッピーディスクシステムよりさらに小型で大容量、ハードディスク並みに高速でデータの読み書きができて、CDと同様の高度な「誤り訂正」機能も採用していました。CDは表面に多少の傷がついたり指紋の跡がついてしまっても、ちゃんと再生できますよね。誤り訂正とは、このように多少メディアや伝送経路が劣化したとしても、ちゃんとデータが記録・再生・伝送できるという仕組みです。当時としては最先端の技術でした。
一方、コンピューターの分野に目を転じると、MacintoshであれIBMからリリースされたPCであるにせよ、モノクロのモニター上に文字や記号がバラバラと並ぶようなものでした。たとえ事務処理用の大型計算機であったとしても、処理にはかなり時間がかかりました。とはいえ、もう少し時間はかかるかもしれないけれど、コンピューターという新たなテクノロジーにはとてつもない可能性を秘めている!と、妄想にも似たロマンを持ち続けていたのです。
そのような妄想を抱くきっかけとなったのが、1968年に公開されたスタンリー・キューブリック監督作品の映画『2001年宇宙の旅』です。SF好きの私は、アーサー・C・クラークの難解な原作を読み耽り、何度もこの映画を観に映画館に通い詰めたものです。この中に登場するコンピューター「HAL」は、IBMのアルファベットを1文字ずつ前にずらしてつけられたというのは有名なエピソードですよね。この映画は半世紀経った現時点で見ても極めて斬新なもので、音声認識システムによるコンピューターとの自然言語による会話はもちろん、生体照合システム、テレビ電話、そしてAI(人工知能)など、2001年には可能になるかもしれない未来技術の登場を実にリアルに描写していました。HALに気付かれないように、その中には、音声的に隔離されたポッド内で交わされる宇宙飛行士の秘密の会話を、HALが唇の動きを読むだけで理解する様子も描かれています。当時はSF映画の世界の中だけの話でしたが、今はこれらのほとんどが現実のものとなっています。その先見性には、あらためて驚かされますよね。
そんな私ですから、情報処理研究所に配属された時は、いよいよその夢の一端を自分でも実現できるかもしれないという思いでワクワクしました。コンピューターというテクノロジーは、オフィスのためだけにあるのではない。そもそもIBMの社名はInternational Business Machinesから由来しているけれど、エンタテインメントのためのコンピューターがあっても良いのではないか?しかもゲーム機のようなリアルタイムの応答性を持った、遊びのためのコンピューター。そんな夢のシステムが実現すれば、今までにない、新たなエンタテインメントコンテンツが続々と生まれるに違いない。そんな想いを募らせていったのです。
当時は、そういったことを考えながらもソニーの研究所でデジタル信号処理技術や情報処理技術の研究を続けていました。時には、自分で回路を組んでピンポンゲームのようなものを作ってスキー場に持って行ってみんなで遊んだこともあります。一緒に行った友人たちが、歓声をあげながら遊んでいるのを見ているのが楽しかったですね。
そんな中で、1983年に発売されたばかりの家庭用ゲーム機を手にして何が驚いたかというと、キャラクターや背景画面がとてもスムーズにスクロールする点なんですね。当時のパソコンやMSXではブロック単位でしかスクロールせず、尺取り虫のような感じで動いていました。それなのに、家庭用ゲーム機ではスーッと滑らかに動きます。それに、何よりもゲームソフトがおもしろかったですね。いろいろ買って、「いいなあ」と思いながらプレイしていました。その頃、ちょうど息子が二人生まれてゲーム機で遊ぶことを覚えると、あっという間に彼らの専用機となってしまいました。子供はパソコンやMSXでは全然遊ばないのに、家庭用ゲーム機では夢中になって遊ぶんですよね。
ただ、当時のゲーム機に関して言うと、私としてどうしても我慢できないことがありました。それは音がひどすぎることです。当時のゲームの音はどれもが「ピコピコ音」という感じで、音の強弱も音の揺らぎも表現できず、和音さえまともに鳴らせないという貧弱なものでした。時を同じくして、音楽シーンではヤマハからFM音源(注1)を内蔵した「DX-7」、KORGからPCM音源(注2)を内蔵した「M1」が発売され、急速にステージで多用されるようになっていきます。
音に様々なニュアンスが加わり、さまざまな音源や楽器が使え、和音が豊富に出せるということは譜面が書けるということです。譜面が書ければ、そこに作曲家やサウンドクリエーター、アレンジャーなど、才能ある人々がゲーム音楽の分野にも入ってくる可能性がさらに広がります。当時は、なぜ家庭用ゲーム機にリッチな音源を使わないのか不思議に思っていましたが、「DX-7」や「M1」は25万円もして、家庭用ゲーム機は1万5千円足らずでしたから、仕方がなかったのかもしれません。それでも「ピコピコ」というゲーム機の音は何とかならないものかと考えていました。その頃、PCM音源にもなりえるDSP(注3)の研究もしていたので、この「ひどすぎるゲームの音源を、一気にPCM音源化してしまえないか」と考え始めたのです。
- 注1:FM音源
- 周波数変調(Frequency Modulation)によって音色を合成する方式を用いた音源。ヤマハDX-7をはじめとするデジタルシンセサイザーのほか、セガ「メガドライブ」などゲーム機の内蔵音源に採用されている。
- 注2: PCM音源
- パルス符号変調 (Pulse Code Modulation)技術によって、メモリに記録されたPCM波形から音を生成する方式の音源。サンプリングシンセサイザーのほか、「スーパーファミコン」や「プレイステーション」の内蔵音源に採用されている。
- 注3:DSP
- Digital Signal Processor、掛け算や加減算といった積和演算セットをプログラムに従って繰り返すことで、音の波形のような時間軸を有する信号の強弱や周波数特性を数学的なデジタル演算処理により可能にする特定用途向けプロセッサ。






